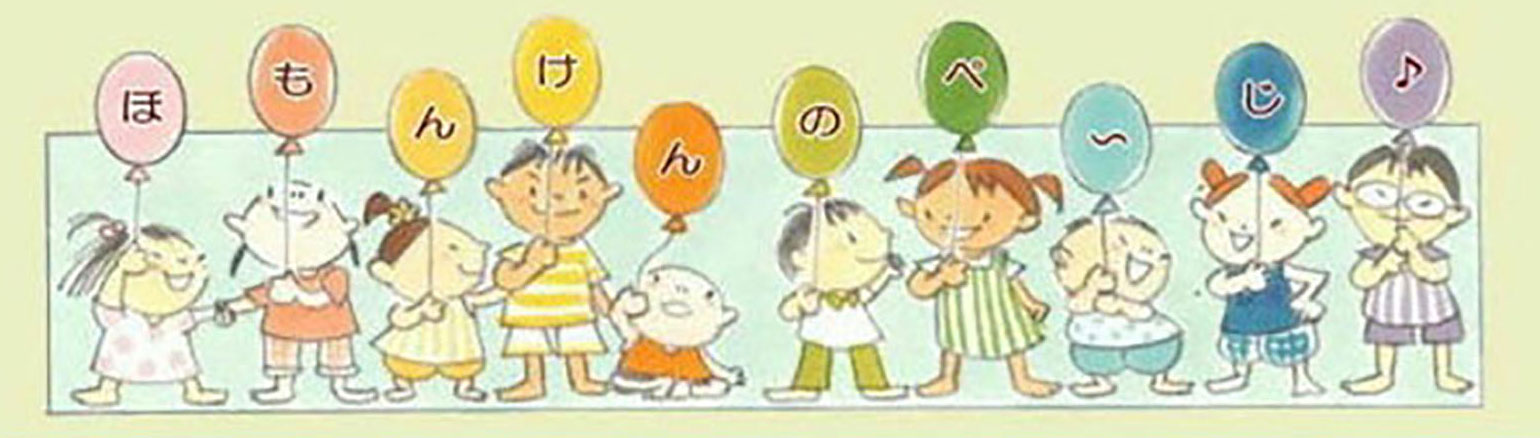◆伝え合いの輪を広げよう
入江慶太 (全国保育問題研究協議会代表・岡山保問研)
保問研は、戦前より一貫して、競争ではなく「共に育ち合う」ことを基盤とした保育のあり方を追求してきました。各地域のサークルの個性を尊重しながら、協議会という緩やかなネットワークを築き、多様性を大切にして活動を進めてきました。こうした保育研究の運動は、今では全国的に広がり、多くの実践と結びついて大きく発展しています。
しかし近年、保育や保育者を取り巻く環境は厳しさを増し、保育条件・労働条件の改善は未だ道半ばです。そうした流れに歯止めをかけ、公的保育をさらに充実させるためにも、私たちの保育研究運動を一層強化していくことが求められています。
まずは、身近なところから。保育について語り合える仲間を見つけ、対話と共有の輪を少しずつ広げていきましょう。
◆全国保問研の活動
戦後東京で再建された保問研は、その後全国に広がり、いまでは、全国各地の40以上の地域で組織され活動しています。
これらの保問研は、全国保育問題研究協議会(全国保問研)をつくって、協力共同の活動を進めています。全国保問研の主な活動は次のようなものです。
・ 年に1回、全国各地を回りながら、全国保育問題研究集会を開催し、一年間の実践と研究の成果を持ち寄り、お互いの共有財産とするよう討論を積み上げています。いまではこの集会には1,000人以上の参加者があります。
・ また、年に1回、テーマを絞った夏季セミナーを開催して、それぞれの問題を深めています
・ 保問研は、機関誌「季刊保育問題研究」(新読書社刊)を年6回発行し、会員相互の実践と研究を交流し、お互いに問題を提起し、討論し合っています。
・ さらに、保問研として討論してきた成果を、テーマ別に『保育問題研究シリーズ』(新読書社刊)として、単行本の発行も行っています。
◆さまざまな活動のあり方
保問研は自主的で民主的な研究団体です。だから、各地の保問研で工夫を凝らした活動をしています。
あそび、乳児保育、発達と集団、障害児保育、絵本、音楽、美術、給食、保育理論、保育政策などの部会活動に、力に応じて取り組んでいる保問研もあれば、 毎月工夫を凝らした例会を持ったり、学習会をしている保問研もあります。また、定期・不定期の機関紙・誌、また研究誌を発行している保問研もあります。
どんな活動に取り組むかは、各地のそれぞれの保問研の自主的な判断で行われていて、固定的なものではありません。いずれにせよ、事実に基づいて、問題を 発見し、それを実践と研究で究明しながら、保育にロマンと科学の光を当てることができればいいなというのが保問研の一致した願いです。そこにはわくわくす るような発見がいっぱいあります。
あなたも保問研で、楽しく話し合ったり問題を深め合ったりしてみませんか。