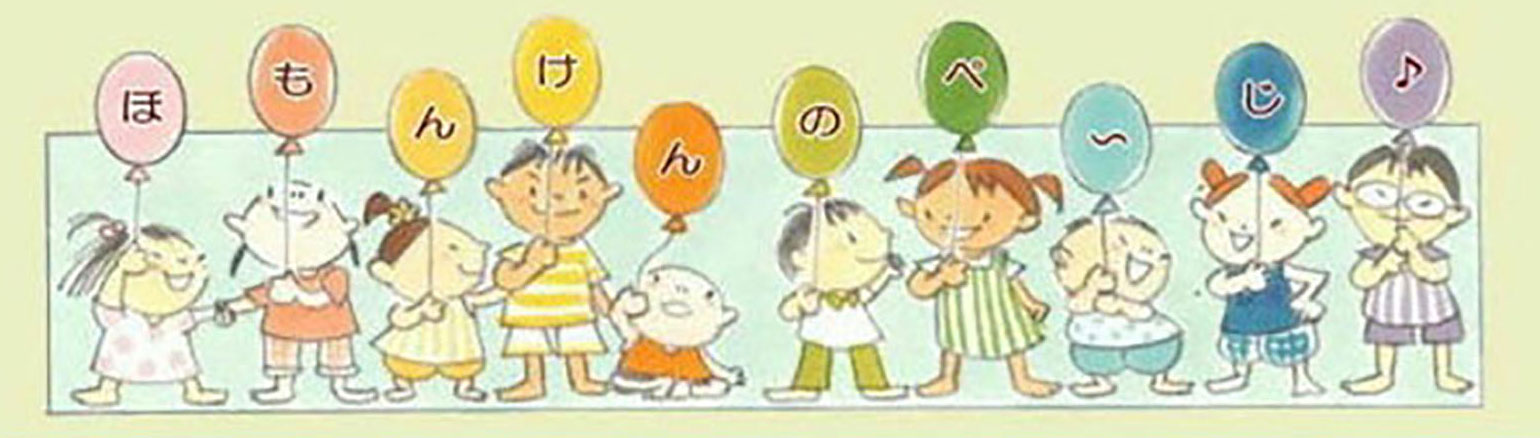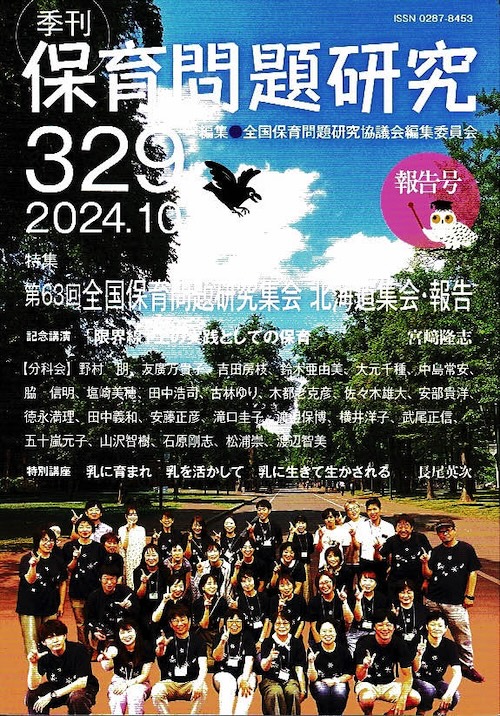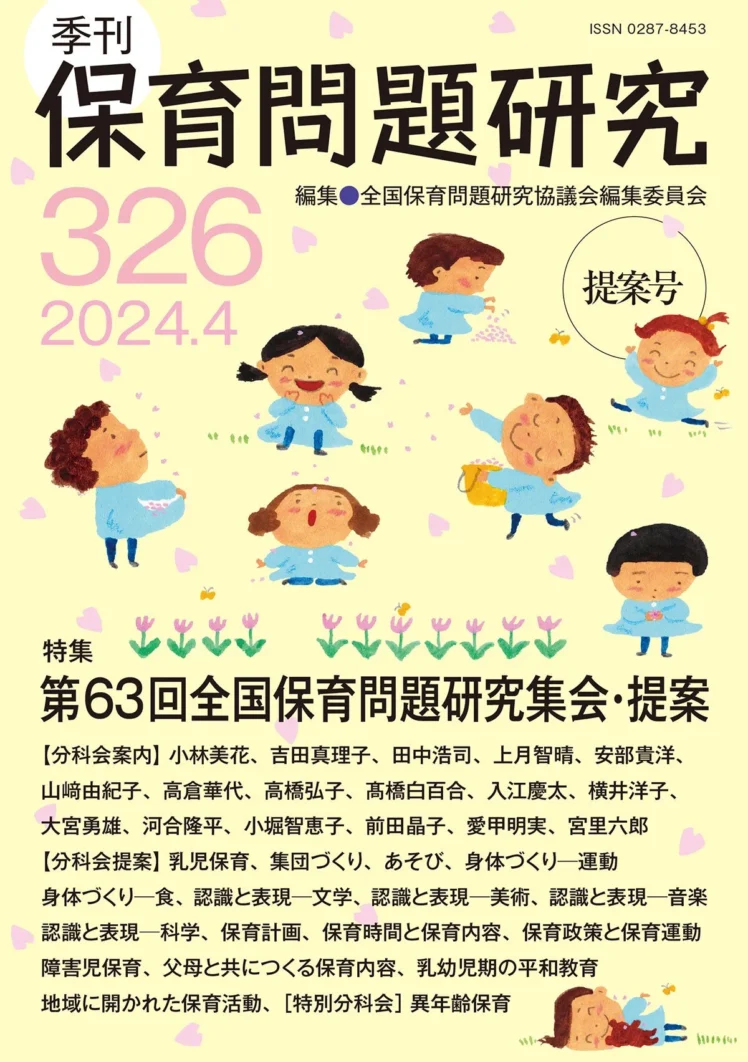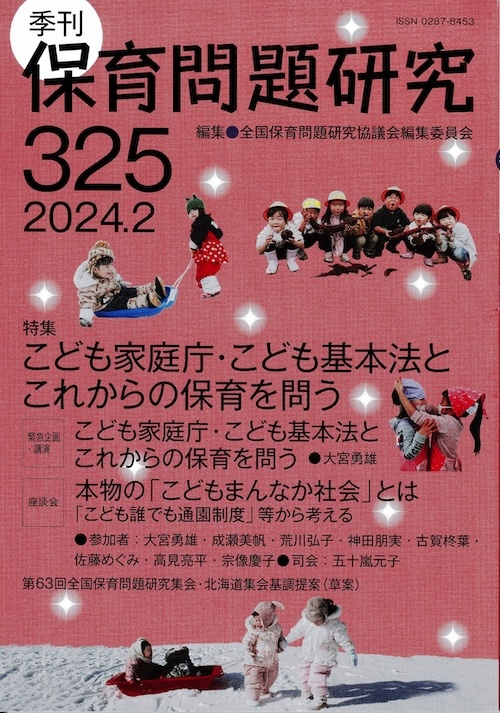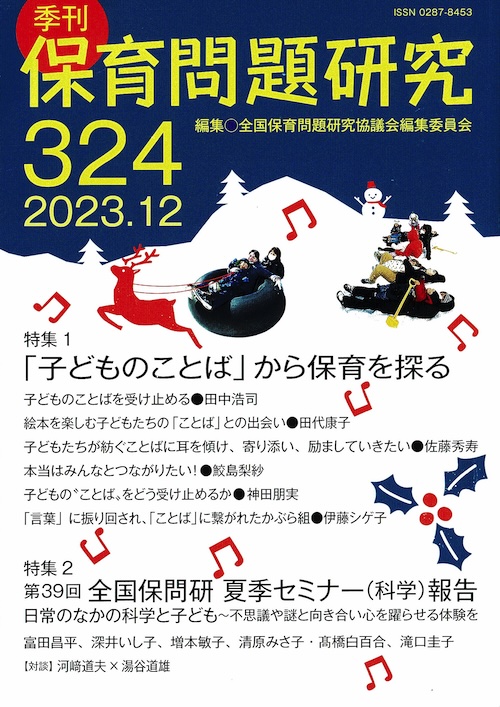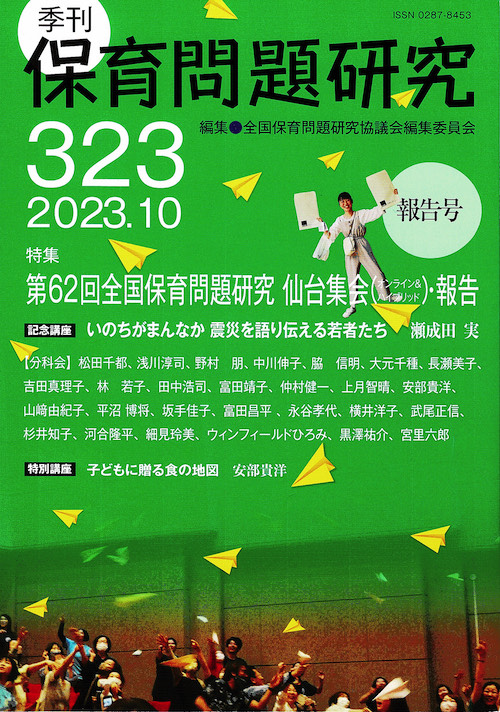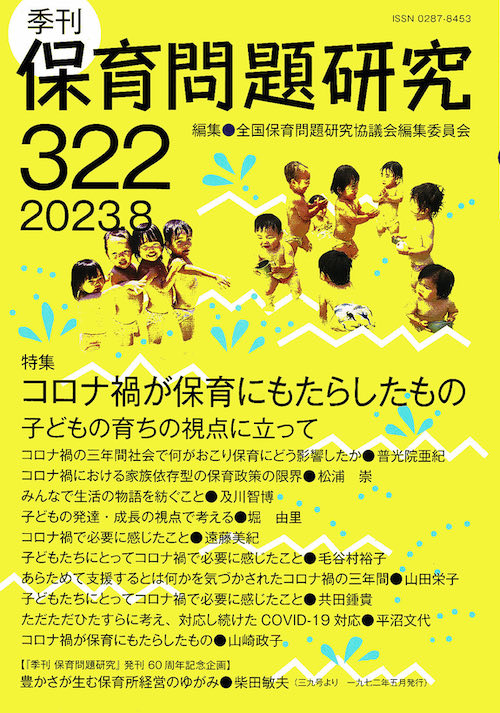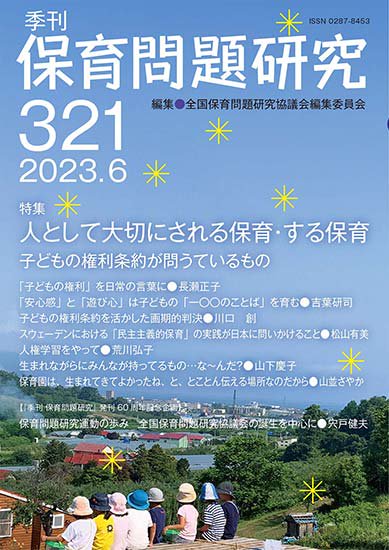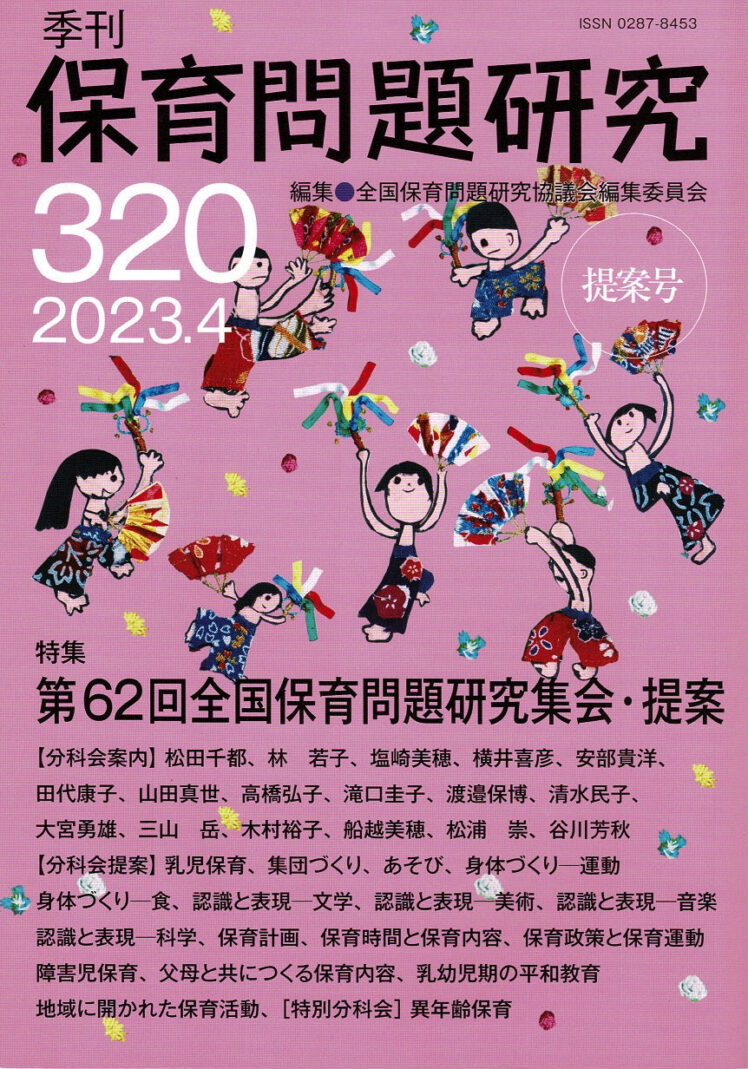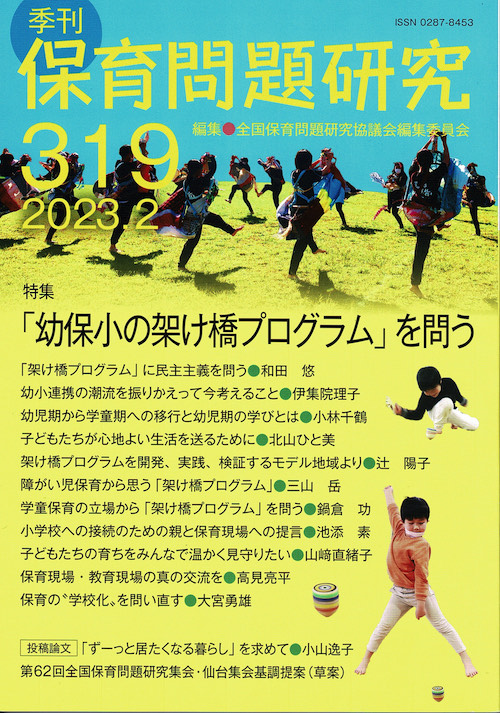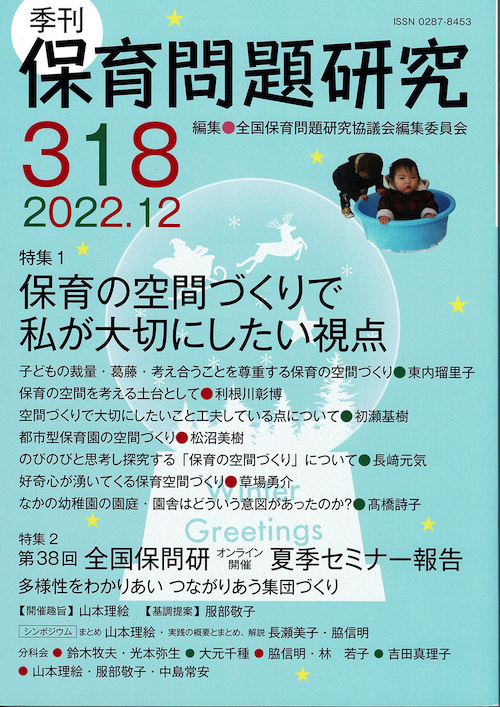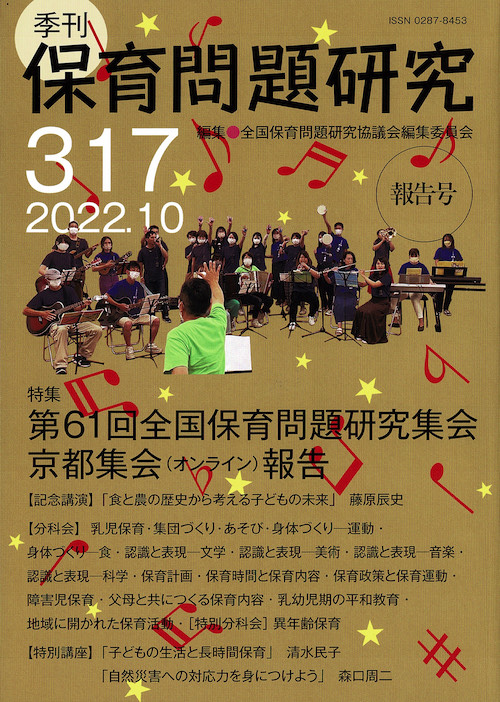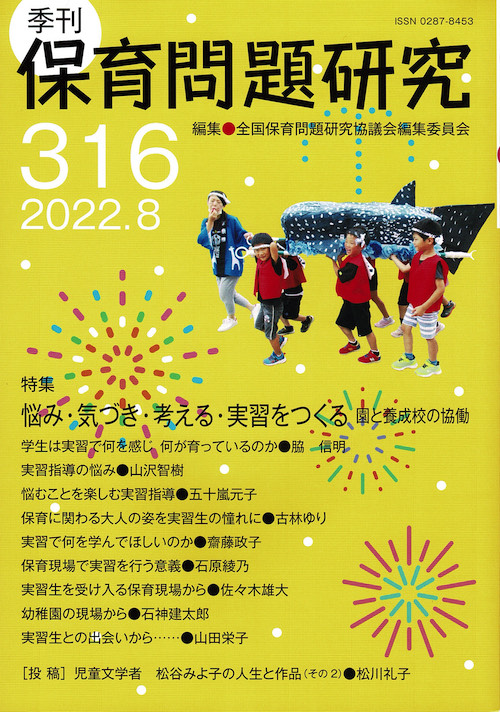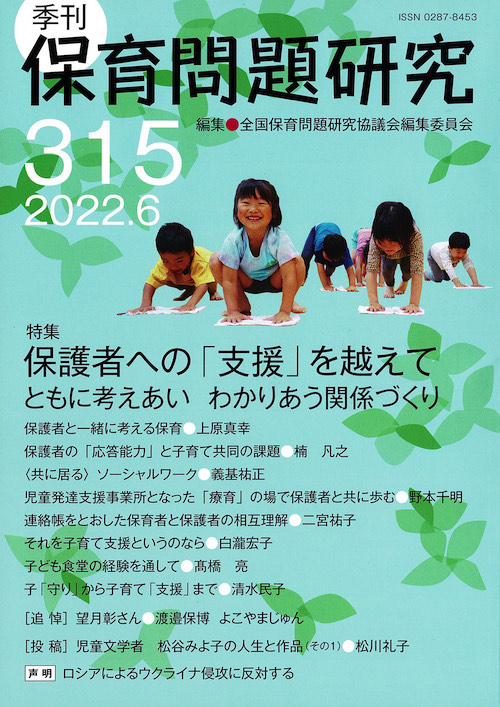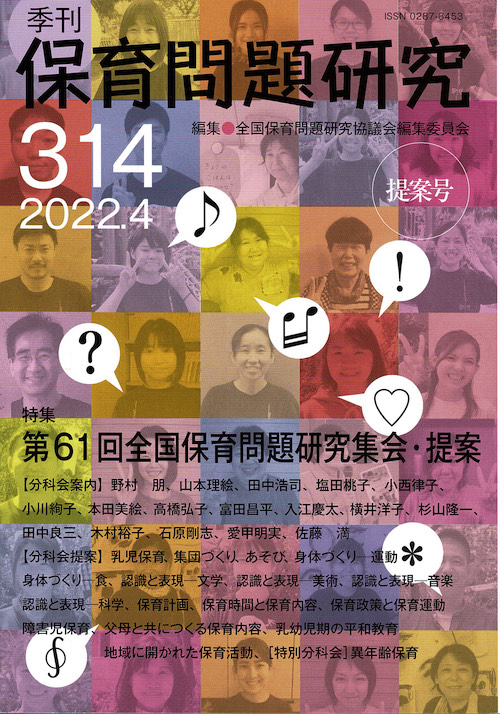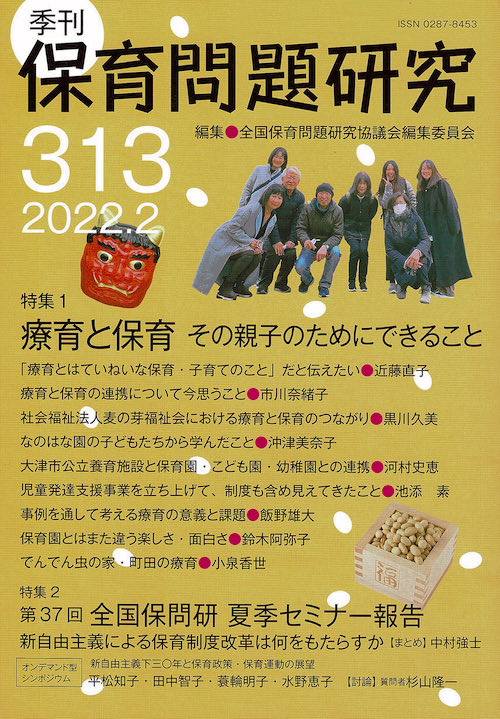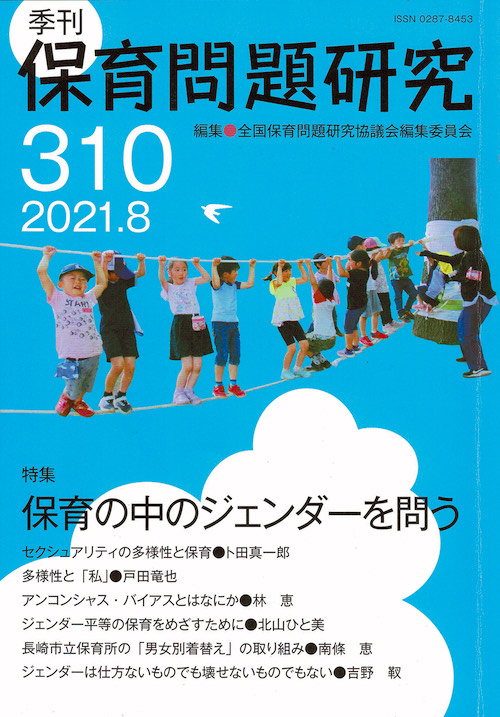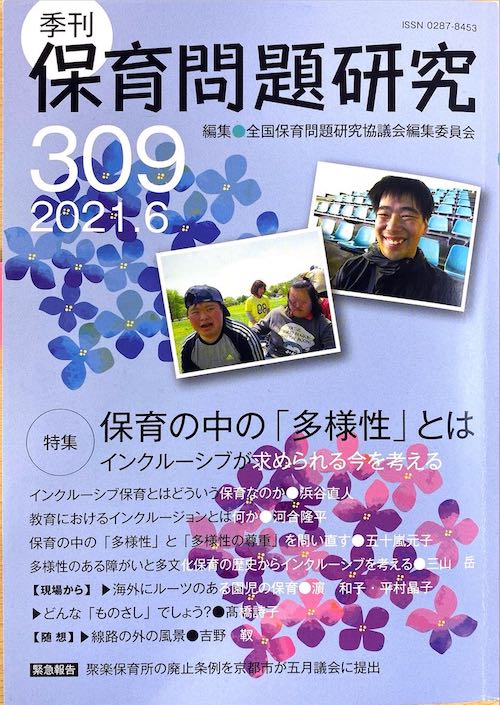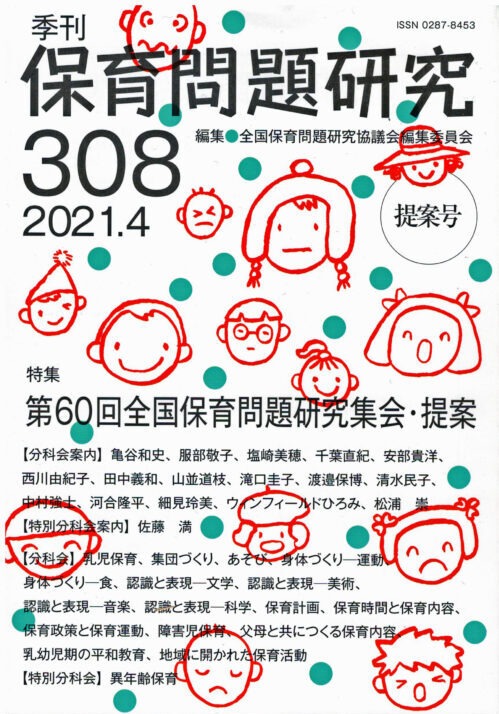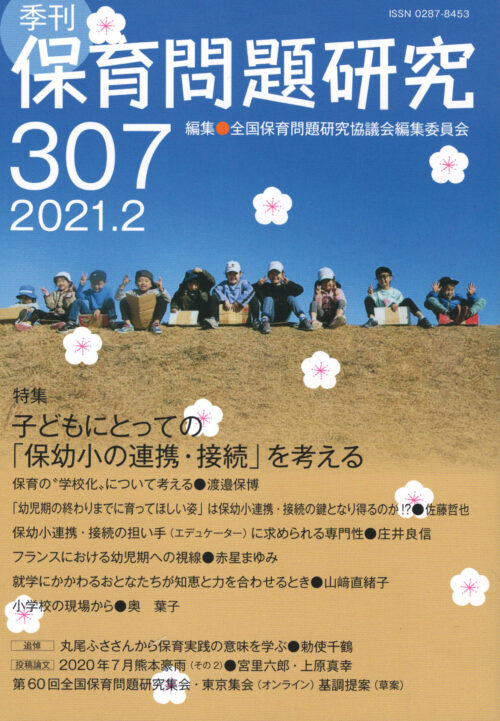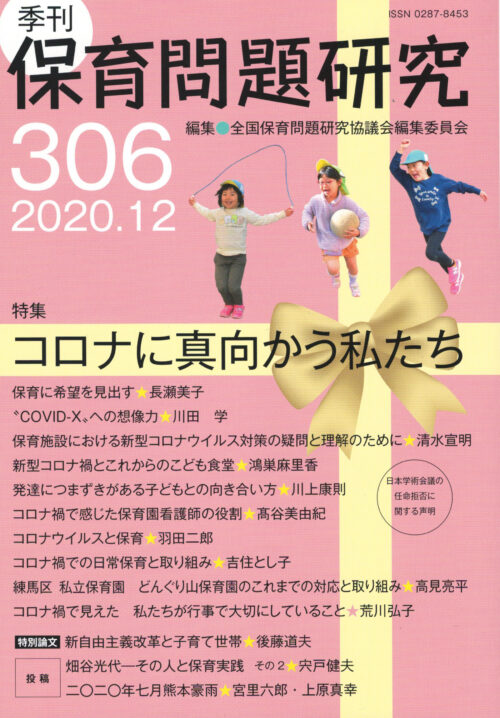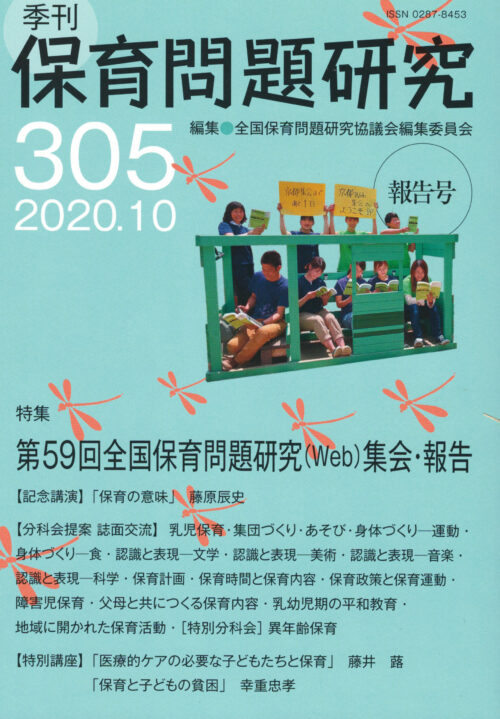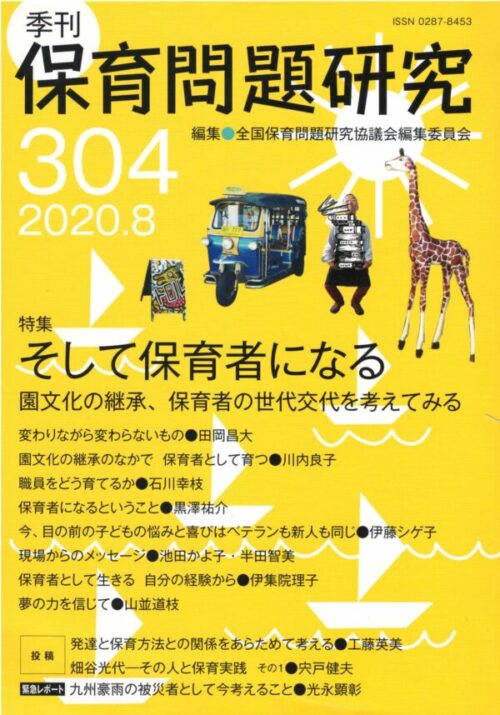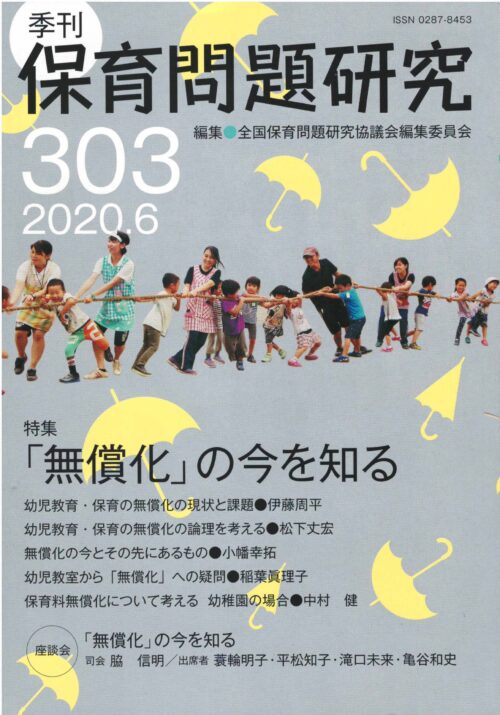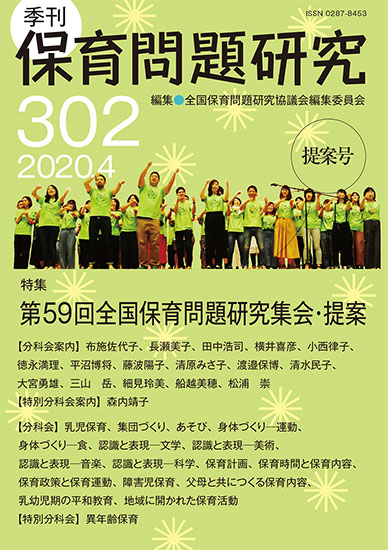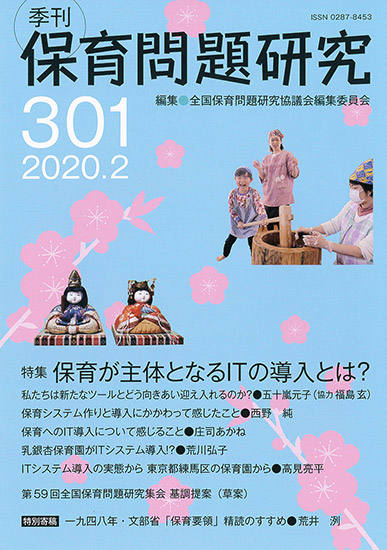『季刊保育問題研究』 全国保育問題研究協議会 編集委員会
1962年に創刊されたこの雑誌は、全国の保育者が互いの活動の状況を報告し合い、運動を進めていく方法について互いに学び合うことができるように、また保育問題研究の視点を提起し合い研究を進めていく方向を理論的に明らかにすることを目的に出版されました。
編集委員長 五十嵐元子
常任編集委員 伊藤シゲ子・神田朋実・増田幸行・田中めぐみ・上原真幸
編集部 伊集院郁夫
A5版 年間6回 偶数月末発行(特集号:年4回 各900円+税 ・ 臨時増刊:2回 各1800円+税)
※年間購読料は、送料含めた設定金額があります。
お申込み・お問い合わせは、お近くの書店か下記の連絡先にご連絡ください。
新読書社営業部 〒113-0033 東京都文京区本郷5-30-20
TEL 03-3814-6791 FAX 03-3814-3097
メール info@shindokusho.jp