「保育問題研究シリーズ」
ご購入は、お近くの書店か、下記の連絡先にお問い合わせください。
新読書社営業部 〒113-0033 東京都文京区本郷5-30-20
TEL 03-3814-6791 FAX 03-3814-3097
メール info@shindokusho.jp
ご購入は、お近くの書店か、下記の連絡先にお問い合わせください。
新読書社営業部 〒113-0033 東京都文京区本郷5-30-20
TEL 03-3814-6791 FAX 03-3814-3097
メール info@shindokusho.jp
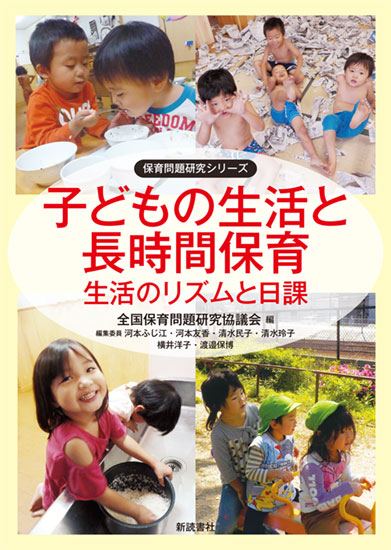 保育問題研究シリーズ
保育問題研究シリーズ 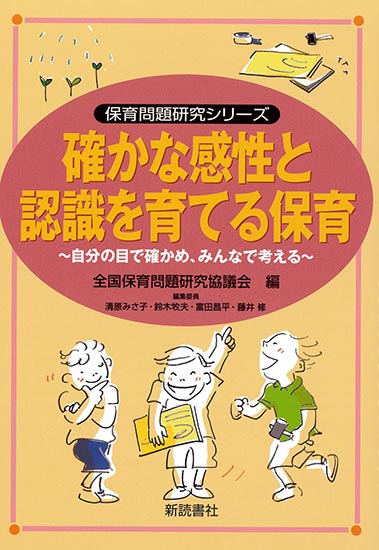 保育問題研究シリーズ
保育問題研究シリーズ 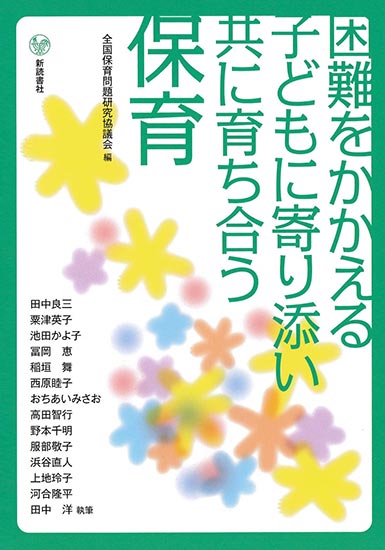 保育問題研究シリーズ
保育問題研究シリーズ 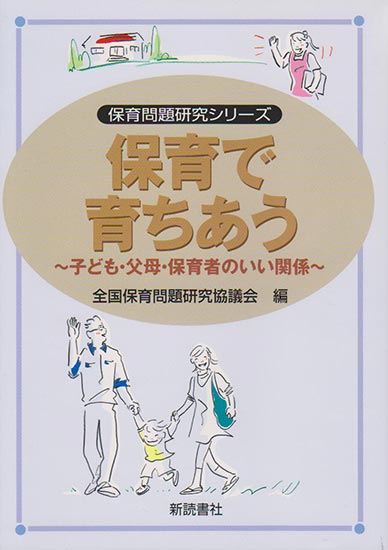 保育問題研究シリーズ
保育問題研究シリーズ 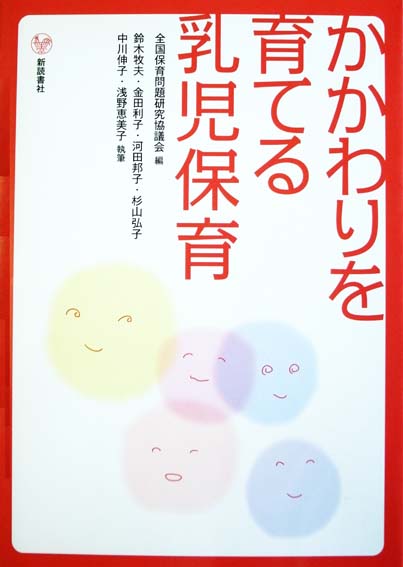 保育問題研究シリーズ
保育問題研究シリーズ 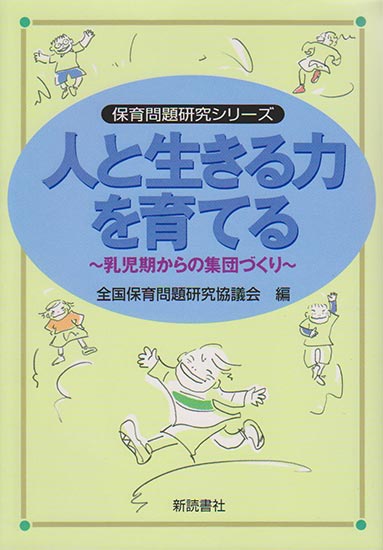 保育問題研究シリーズ
保育問題研究シリーズ  保育問題研究シリーズ
保育問題研究シリーズ 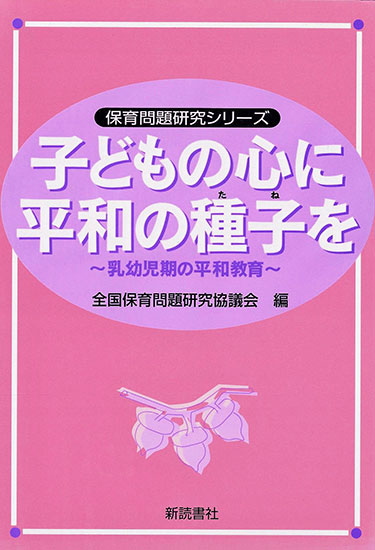 保育問題研究シリーズ
保育問題研究シリーズ 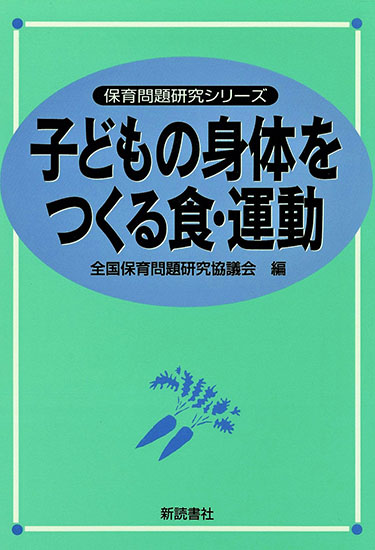 保育問題研究シリーズ
保育問題研究シリーズ